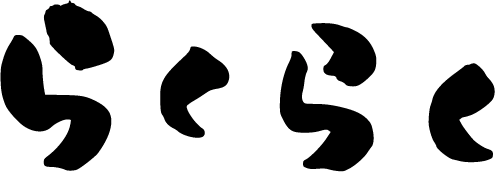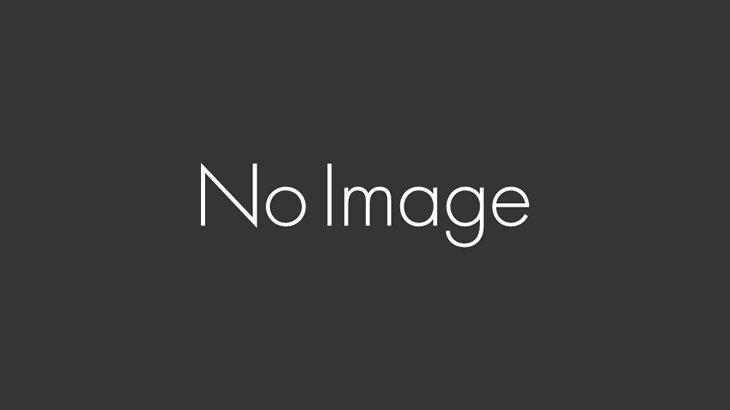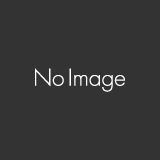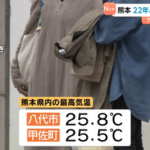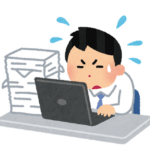受刑者が“記者”に。東京拘置所で記事の書き方講座 取材から執筆まで、社会復帰へコミュニケーションや発信磨く
https://news.jp/i/1323514435139551878
Published 2025/08/24 09:00:00
Updated 2025/08/18 13:31:43
受刑者に記事を書いてもらおう。東京拘置所(東京都葛飾区)で2024年度、初の試みとして共同通信記者による記事の書き方講座が開かれた。初対面の人と向き合い、質問を重ねて話を聞き出し、記事にまとめるまでを経験。取材時に求められるコミュニケーション能力や、執筆で必要なまとめる力を磨くことで、円滑な社会復帰に役立ててもらうのが狙いだ。
記事完成までの過程では、受刑者間で活発なやりとりも繰り広げられた。「カギ括弧が少ない」「もう少し削れば別のエピソードを入れられる」。編集の現場さながらの白熱した意見交換に、講座に立ち会った拘置所の職員も記者自身も驚かされた。(共同通信=今村未生)
▽記者会見形式
講座は2024年8月から2025年1月まで6回開かれた。参加したのは30~40代の男性受刑者4人。まず、新聞紙面の構成などについて学んだ。その後、出所者を雇用する「協力雇用主」の建設会社社長、高橋政志さん(55)を招き、記者会見形式でインタビュー取材を実施した。
最初は互いにぎこちない様子。受刑者側は質問が早口になり、高橋さんも緊張のためか表情が硬かった。取材が進むにつれて次第に笑顔が見え、雰囲気がほぐれていった。質問は1人1つずつで、順番に回す形。受刑者からは「出所後、気を付けるべきことは」「罪を犯した人を雇うことで、不利益を被ったことはあるか」との質問も。インタビューは約1時間に及んだ。
高橋さんは「彼らが“記者”としてしっかりとした質問をしてきた」と驚いた様子。「聞いたり発信したりする力が付くと、社会復帰に役立つのではないか」と、協力雇用主として多数の出所者と向き合った経験を踏まえて感想を語った。
▽発信側の視点
拘置所内の居室ではパソコンを使用できない。そのため、施設側が新聞の規格に合わせた原稿用紙を用意した。受刑者たちは高橋さんの人となりや経歴に関する記事を執筆。それぞれが書き上げた記事を持ち寄り、全員の前で発表した。その後、互いにアドバイスし合い、いったん持ち帰って後日書き直して完成させた。
今年5月、講座を振り返っての感想を聞かせてくれた。40代の受刑者は「本当に伝えたいことを書こうと何度も見直して、ぎりぎりまで練った」。別の40代の受刑者も「知らなかったマスコミの世界を知ることができた。報道側の気持ち、発信する側の視点で物事を見ることができたのが興味深かった」と話す。30代の受刑者は「作文との違いはたくさんの読み手を想定すること。そうした経験は多くはなく、ためになった」と振り返った。
法務省の成人矯正課長だった森田裕一郎さん(現・名古屋刑務所長)は「相手の言うことを受け止め、正しく外部に伝える力を付けることは、コミュニケーション能力の養成につながる。再犯防止を目指す上でも非常に大切だ」と話した。
東京拘置所では死刑囚を含めて常時約2千人を収容している。大半は裁判が続いている被告だ。2千人のうち受刑者は約250人で、施設運営に必要な食事の提供や洗濯などの作業に従事している。
▽新たなスタイル
米カリフォルニア州のサン・クエンティン刑務所では、外部の協力を得て、ネット上で所内の様子などを発信する先進的な取り組みが行われている。受刑者が編集長や記者を務める「サン・クエンティンニュース」というメディアで、刑務所内で開催されたイベントやスポーツ大会の様子や、法律や矯正施設での出来事といった受刑者に関係しそうな外部のニュースなどを精力的に発信。ホームページのほか、交流サイト(SNS)でも伝え、ジャーナリズムの観点からも高い評価を受けている。
東京拘置所での講座は、米国での取り組みに着想を得たものだ。
(略)「発信者の意図を知ることで、出所後もSNSの誤情報に惑わせられないのではないか」との意見もあった。いかに取材を重ね、慎重に記事を書いているのか、その一端が少しでも伝わったとすれば、講座を実施して良かったと思う。
※全文はソースで