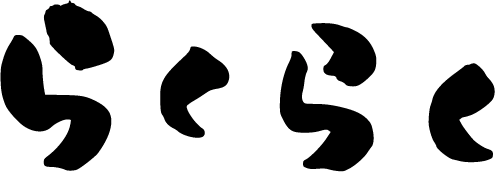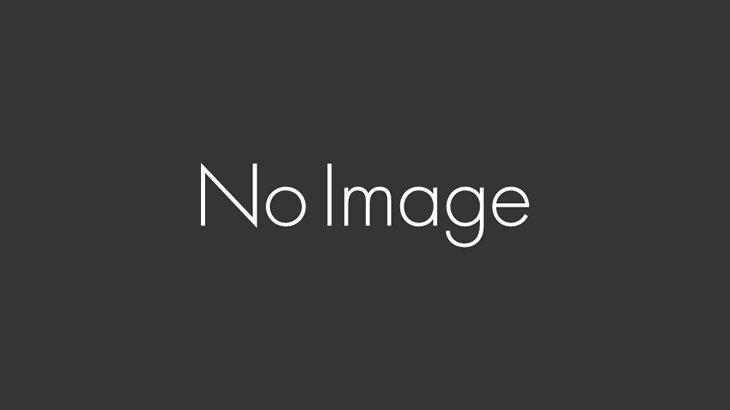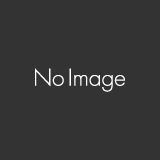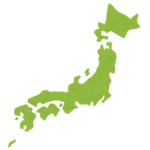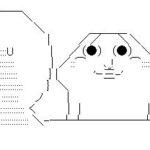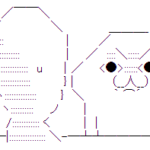年収300万円未満の人の半分近くが「国内旅行に行ったことがない」日本人の移動にまつわる格差
https://bunshun.jp/articles/-/81495
「はじめに、衝撃的な数字を共有したい。それは、過去1年以内に居住都道府県外への旅行経験がない人の割合が、年収600万円以上の人だと18.2%、年収300万?600万円未満の人は30.7%、年収300万円未満の人は45.6%という調査の結果である。つまり…」
調査でわかった「日本人の移動にまつわる格差」とは? 国際大学グローバル・コミュニケーション・センター研究員・講師の伊藤将人氏の新刊 『移動と階級』 (講談社)より一部抜粋してお届けする。(全2回の1回目/ 後編を読む )
「21世紀は観光の時代である」というスローガンは、学術と産業の両方で多用されてきた。いまや国境を越える観光客の増加は全世界的な傾向であり、観光産業は21世紀の最も有望な成長産業の一つであるともいわれている。
学術的にも、人文社会科学が捉えようとしてきた「社会的なもの」は、今や「観光」にこそ明白に現れると言われており(遠藤:2017)、ジョン・アーリとヨーナス・ラースンの『観光のまなざし』や哲学者の東浩紀による『観光客の哲学』、社会学者の遠藤英樹による『ツーリズム・モビリティーズ』など、観光・観光客という概念を鍵に現代社会を思考する試みも多くなされている。資本主義、グローバル化、消費社会、そして移動、観光には現代社会を特徴づける要素が詰まっているのである。
実際、いま世界には推定12億8600万人の国際観光客(宿泊客)がいる。さらに、観光産業は世界のGDPの9?10%を占めるほどになっている。
そんななか、猛威をふるった新型コロナは観光業を壊滅的な状況に陥れた。今では、ほぼコロナ禍前の水準まで観光産業は復活したが、あの経験を忘れることはできない。
より中長期的に国境を越えて移動する移民や難民にも目を向けてみると、国際移住者は推定2億8100万人、紛争や暴力、災害、その他の理由による避難を余儀なくされた国内避難民の数は1億1700万人にも達している。移民の経済活動は世界全体のGDPの1割に相当しており、これはアメリカや中国の割合に次ぐ大きさである。移動は大国と同じだけの経済的影響を、世界に与えているというわけだ。国境を越える移動者をめぐる格差を考え、明らかにする意義が、わかっていただけただろうか。
■約3人に1人が、過去1年以内に居住都道府県以外に旅行していない
そこでまずは、回答者の過去1年間の旅行経験からみてみよう。以降、「過去1年間」という場合は、2023年10月から2024年10月までの1年間を指している。
この分野においては、公益社団法人チャンス・フォー・チルドレンが、子どもの体験格差をテーマに類似の調査を行っている。それによれば、観光旅行は、数ある文化的体験の中で、世帯年収の多寡で生じる“体験格差”が最も大きい。旅費交通費などの支出が避けられず、保護者の時間的余裕も必要なことが理由である。本書調査は、主に大人の移動経験と移動格差を調査対象とする点が、チャンス・フォー・チルドレンとの違いである。
はじめに、衝撃的な数字を共有したい。それは、過去1年以内に居住都道府県外への旅行経験がない人の割合が、年収600万円以上の人だと18.2%、年収300万?600万円未満の人は30.7%、年収300万円未満の人は45.6%という調査の結果である。つまり、居住都道府県外への旅行をめぐって、年収600万円以上の回答者と300万円未満の回答者で、およそ27%ポイントもの差が存在するのである。
“誰もが観光旅行できる時代”といわれる現代においても、実際には一定以上の距離の移動を伴う観光旅行経験には、年収、社会階層による格差が生じているのである。
■階層によって2倍以上の差がある海外渡航経験
国内旅行経験の実態を知ったら、海外渡航経験も気になるところである。2020年以降の移動をめぐる状況は新型コロナの影響が少なからずあり、調査時点では十分に状況が回復していなかった。特に、海外渡航となると避けている人も一定数いると思われる。そこで、これまでの人生におけるすべての海外渡航経験について質問した。
その結果、娯楽目的の海外渡航経験がない人は、年収600万円以上の人で20.5%、年収300万?600万円未満の人で33.2%、年収300万円未満の人で46.3%という結果となった。海外渡航経験についても、年収300万円未満の回答者と、600万円以上の回答者では、約26%ポイントもの差があったのである。
さらに、300万円未満だと海外旅行を1年に1回も経験しない人が、約2人に1人であるのに対して、600万円以上だとそれは約5人に1人という実態も浮かび上がってきた。行き先の国内国外を問わず、観光旅行をめぐる移動機会には決して小さくない格差がたしかに存在するのである。
※以下出典先で