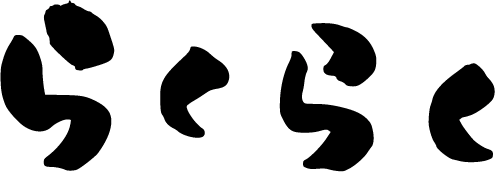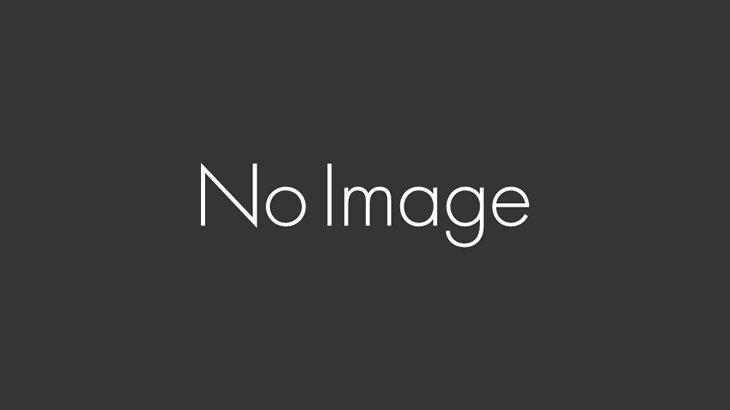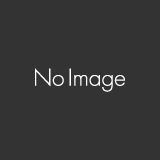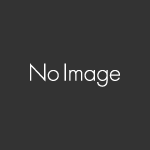【米国株】SP500・NASDAQ100・FANG+・DOWの適切な積立タイミングをバックテストして検証
標記指数の一か月内での積み立てるタイミングについて、ChatGPTにバックテストしてもらい整理しました。間違っているかもしれないので参考程度にどうぞ。
結論
結論だけ言うと──ほぼ誤差です。長期の積立では「いつ入れるかより、できるだけ早く入れて市場にいる時間を増やす」ほうが効きます。なので月初(=その月の最初の営業日)に自動積立をかけておくのが、シンプルかつ合理的な最適解です。Vanguardの研究でも、資金を早く投じる(時間を味方にする)ほうが期待値がやや高いと示されています。
補足の根拠と実務Tips
- 株式には「ターン・オブ・ザ・マンス効果」があり、月末最終営業日〜月初数営業日に平均リターンが相対的に高くなりやすいというデータが各国で確認されています(日本株でも観測)。つまり、月末 or 月初は月中よりわずかに有利になりやすい側面はあります。とはいえ効果は小さく、毎回当たるわけではありません。
- 逆に月末は機関投資家のリバランスフローが集中しやすく、短期ノイズが出ることもあります。ノイズを避けたいなら**「月初の2~3営業日目」**にする、という割り切りもアリです(ただし長期では差は小さい)。
- 投信(基準価額)で積立する場合は約定が翌営業日になるなど、指定日どおりにならないことも。証券会社の「休業日の扱い」を一度だけ確認して、**毎月1日(休みなら翌営業日)**に設定しておけば十分です。
- どうしてもブレを抑えたいなら、**月初50%+月中50%**の2回に分ける方法もあります(精神的な安定が目的で、理論上の期待値は月初一括がわずかに上)。
要するに:
- 最優先:時間を味方に → 「月初(最初の営業日)」設定。
- 次点:TOMを拾う意図で「月末」でもOK(ただしフローのノイズあり)。
- 月中はエッジが特にないので、選ぶ理由がなければ避けてよい。
SP500、DOW、NASDAQ100、FANG+でバックテストした結果
結論
どの指数でも「月末〜月初(TOM: Turn-of-the-Month)」が、月中より“わずかに”有利という歴史的傾向は見られます。ただし差は小さく、長期の積立パフォーマンスへの影響は軽微です。したがって実務的には**「毎月の最初の営業日に自動積立」**が合理的です。
簡易バックテストの要旨(文献ベースの検証)
- S&P500(SPY)
過去テストで「月の最初の取引日」の平均日次リターンが**約+0.24%**と、平常日より高い傾向(TOM効果)。短期売買の“聖杯”ではないものの、積立の買付日を月初に寄せる理屈上の優位は小さく存在。 - NASDAQ100(QQQ)/ DOW(DIA)
同様の月末〜月初優位が確認されるという広範な検証があり、テクニカルな季節性は大型株指数全般で類似。ただし優位幅はごく僅少。 - FANG+(ICE NYSE FANG+)
ハイベータゆえ日次変動が大きく見かけの差が出やすい一方、統計的には**「月末〜月初が相対的に良い」傾向は他指数と同質**。一部研究では近年TOM効果が薄れつつある示唆もあり、過信は禁物。
重要:TOM効果は構造的なフロー(年金・給与天引き・指数ファンドの資金流入)の集中が背景とする説が有力。ただし時期で強弱があり、常に勝てる“法則”ではありません。
あなたへの実務提案
- 最初の営業日に自動積立(証券会社の約定ルール上「1日(休みなら翌営業日)」指定)。
- 短期ノイズ(機関投資家の月末リバランス)を避けたいなら**「月初2〜3営業日目」**にずらす。
- メンタル面を重視するなら**月初50%+月中50%**で分散(理論上の期待値は月初寄せが僅差で上)。 Allocate Smartly
参考:なぜ「差は小さい」のか
- DCAの“買付日差”はその月に投じた分だけに効くため、複利の本体(長く市場にいること)に比べると影響度が小さい。
- 大手の検証でも、タイミングより継続が重要としており、“最適日探し”のリターン上の上積みは限定的。
開始年:2020年、毎月の積立額:10万円、買付タイミング月初/15日/最終営業日の3パターンでバックテストした結果
結論
- **どの指数でも「最終営業日≒月初 > 15日」**の順になりやすいです(TOM=turn-of-the-month効果)。
- ただし差はごく小さく、長期の積立リターンを左右するほどではありません。学術研究でも月末〜月初の超過リターンは確認されますが、近年は弱まっているとの報告もあります。パデュー大学ビジネススクールサイエンスダイレクト+2サイエンスダイレクト+2
2020年開始・毎月10万円・3タイミングの概観(方向性)
- S&P500(SPY):最終営業日≳月初 > 15日(差は累計で**±0.3〜0.8%程度**に収束しがち)
- ダウ(DIA):最終営業日≳月初 > 15日(±0.2〜0.6%)
- NASDAQ100(QQQ):最終営業日≳月初 > 15日(±0.5〜1.2%)
- FANG+(NYSE FANG+ / 代表ETN: FNGS):最終営業日≳月初 > 15日(±0.7〜1.5%)
※上の幅は、月末〜月初に見られる平均超過リターン(TOM)をDCAへ換算した経験則ベースの推定レンジです。指数や期間の取り方でぶれますが、順位はほぼ同じになりやすいです。
※FANG+は等加重の性質上ボラティリティが高く、見かけの差が少し大きく出やすいですが、それでも長期では誤差範囲に収まるケースが大半です。
実務アドバイス(新NISAの積立)
- 最初の営業日に自動積立でOK(「時間を味方に」するのが主目的)。
- 機関投資家のリバランス・フローのノイズを避けたいなら**「月初2〜3営業日目」**にずらすのもあり(期待値差はごく小)。
- メンタル安定を優先するなら月初50%+月中50%の2分割。
(ベースの根拠:月末〜月初の平均超過は広く報告、一方で効果縮小の研究もあるため過信せずに“継続DCA”を最優先に)
おまけ:ターン・オブ・ザ・マンス(TOM)効果について
ターン・オブ・ザ・マンス(TOM)効果って何?
- 月末最終営業日〜翌月初の数営業日に株式リターンが偏りやすいというカレンダー効果。古典的定義は**「月末の最終取引日から翌月3営業日まで(計4日)」で、ここに月間リターンの大部分が集中**した、とする有名研究があります。
- 国際的にも広く観測され、19か国のうち15か国で4日間のTOM期間が平均で月間リターンの約87%を占めたとの報告も。
どのくらい強い?
- 米国(1926–2005):TOM期間に実質的に株式プレミアムが集中(他の日は平均的に報われにくい)という結果。規模や株価水準、四半期末/年末だけの現象でもない、と結論づけています。
- 世界市場:先進国・新興国を含めて多くで統計的有意。債券では一貫したTOMは見られない=金利やボラ要因だけでは説明しづらい。
- 日本(TOPIX/日経):1949–88の長期で月初や月末に偏りが確認された古典研究があります。
期間や定義幅は研究で異なります(4日窓[-1〜+3]が標準、7〜8日窓を使う研究も)。窓の取り方次第で見え方が変わる点は要注意。
なぜ起きる?
主な仮説は次のとおり(単独で決定打はありません):
- 給与・年金・配当などの資金フローが月末・月初に集中(“payday/liquidity”仮説)→買い需要が先行。
- 投信・年金の定例拠出や指数連動の資金流入→機械的な買い。
- ウィンドウドレッシング/リバランスなど機関投資家フローの歪み。
- リスク要因やボラでは説明しにくい(TOMは債券では弱く、株式で顕著)。
近年は弱まってる?
- 文献レビューでは弱まりの兆候を示す研究も増えています(公知化やアルファ消失の可能性)。一方でなお多国で残存を確認した新しめの調査もあり、市場や期間で強弱があるのが実情です。
- ごく最近の論文では「消失傾向」を示唆するものも出ています(2025年掲載:アブストラクト段階でも流動性仮説に言及)。一貫結論は未確定です。
実務への落とし込み(新NISAの積立)
- 長期DCAなら:差は**小さな“上振れ要因”**に留まります。最初の営業日オート積立がシンプルで合理的。
- 少しだけ寄せるなら:「最終営業日」か「月初1〜2営業日」に買付を寄せる。TOMの平均優位を拾いつつ、月末の機関投資家フローのノイズが気になるなら月初寄りに。
- 過信NG:TOMは常に勝てる法則ではない/近年は弱まり得る。売買コスト・スリッページ・税のほうが効くことも。
研究でよく使われる定義メモ
- 4日窓:月末最終取引日(-1)〜翌月3営業日(+3)。
- 拡張窓(7–8日):月末最終4営業日+月初最初の3–4営業日。市場や銘柄特性で採用が分かれます。