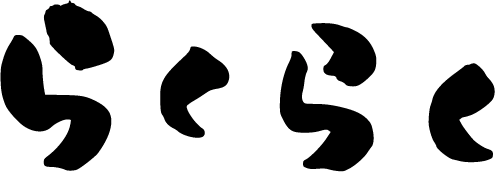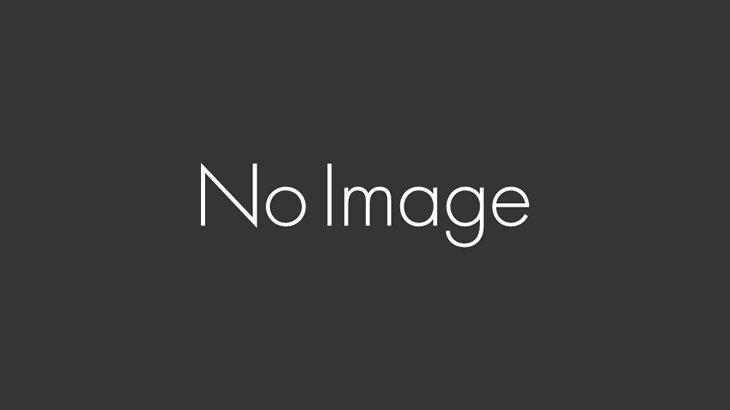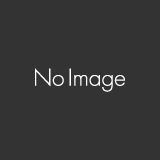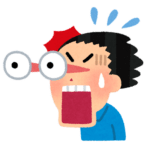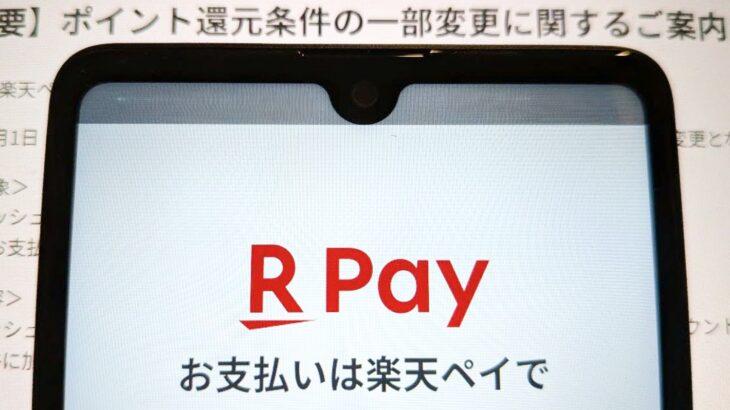【日本株・米国株】石破首相辞任に伴う日本株及び米国株への影響について
石破首相辞任に伴う日本株及び米国株への影響をChatGPTに整理してもらいました。間違っているかもしれないので参考程度にどうぞ。
事実関係
日本時間で昨日(2025年9月7日)、石破茂首相が退陣を表明しました。これを受け、与党・自民党は緊急の総裁選(10月上旬見込み)に移行、候補として高市早苗氏、茂木敏充氏、小泉進次郎氏らの名が挙がっています。発表直後は「円安進行」+「超長期国債利回り上昇(価格下落)」といった“政治不確実性プレミアム”を織り込む動きが目立ちました。
日本株への影響(短期→中期)
短期(〜数週間)
- ベースシナリオ:政権移行の不透明感=円安・JGB売り(利回り上昇)バイアス継続。株式は外需・金利上昇の恩恵セクターが相対強。
中期(総裁選〜新内閣発足まで:1〜2か月)
- 政策手掛かり待ちで物色はローテーション。候補の政策スタンス(拡張財政か、財政規律重視か)で為替・金利・業種の強弱が変化。
恩恵を受けやすい(順)
- 輸出主力(円安メリット):自動車(7203トヨタ、7267ホンダ、7270スバル)、重機(6301コマツ)、電機・半導体製造装置(8035東エレ、6857アドバンテスト、7735スクリーン)
- 生保・損保(長期金利上昇):8750第一生命HD、8795T&D、8725MS&AD(資産運用利回り改善)
- メガバンク(イールドカーブスティープ化):8306三菱UFJ、8316三井住友、8411みずほ(NIM拡大余地。ただし保有債券の評価変動リスクは留意)
- インバウンド関連(円安×訪日需要):鉄道・空港・ホテル・テーマパーク等(指数ではインバウンド色の強い銘柄群)
逆風(順)
- J-REIT・高配当ディフェンシブ(利回り上昇=相対魅力度低下):東証REIT指数・電力ガス(規制セクターは金利敏感)
- 内需インポーター/小売:仕入れコスト増(家具・生活雑貨・衣料など)。為替ヘッジや海外展開次第で度合いは銘柄差。
- 公共料金コストに敏感なセクター:燃料・資材の輸入価格上昇が利益圧迫要因。
補足:いずれも**“円安+長期金利上昇”という足元のマーケット反応**に基づくインプリケーションです(政策確度が見えるまでの暫定バイアス)。
米国株への影響
- 為替換算の逆風:円安は日本売上のUSD換算を押し下げるため、ジャパンエクスポージャーの大きい米多国籍企業(消費・ラグジュアリー・外食・アパレル・ゲーム等)は報告数字上のマイナスが出やすい(実需は不変でも翻訳差損)。これは一般論としてのFXトランスレーション効果に基づく評価です。
- 日本エクスポージャーETF:米上場の日本株ETFでは**通貨ヘッジ型(DXJ)**が円安局面で相対優位、**非ヘッジ型(EWJ, JPXNなど)**は円安で円建て株高を相殺されやすい。
- 金利上昇→グローバル金利連動のセンチメント:日本の超長期金利上昇は世界債券にも連鎖しやすく、金利敏感の米リート・高バリュエーション銘柄にはセンチメント悪化が波及する可能性。
後継別シナリオ(政策×市場の型)
- 高市早苗氏(拡張財政寄り)
- 市場観:円軟化・長期金利上昇バイアス継続 → 輸出・金融(生保/銀行)>REIT/ディフェンシブ
- 公共投資色が強ければ**ゼネコン(1802大林、1803清水 等)**も循環的に強含み。
- 茂木敏充氏(中道路線・対米交渉に強み)
- 市場観:不確実性後退で円の自律反発も。過度な金利上昇が沈静化なら内需やREITのリリーフが入りやすい。
- 小泉進次郎氏(中道・環境色)
- 市場観:政策の方向性は漸進的。グリーン投資・循環経済関連がテーマ化の余地、為替・金利は中庸。
使える実務アクション(手早く)
- 指数・ETFの使い分け:円安継続を見るなら為替ヘッジ日本株(DXJ)、円反発を見るなら非ヘッジ(EWJ/国内ならTOPIX連動)。
- セクターバランス:短期は輸出・保険・銀行をオーバーウェイト/REIT・規制ディフェンシブをアンダー、新政権の政策が見えたら段階的にニュートラルへ。
- 個別の例(日本):恩恵=トヨタ/ホンダ/コマツ/東エレ/アドバン/第一生命/三菱UFJ、逆風=J-REIT指数・一部インポーター・電力ガス。
- 米国保有資産の管理:決算シーズン前にJPY感応度の高い売上比率を確認、必要なら**簡易ヘッジ(先物/オプション/通貨ヘッジETF)**で翻訳影響を緩和。
重要指標のチェックポイント:①総裁選日程と公約、②USD/JPYと円金利(特に超長期)、③内需系指標(百貨店・訪日統計)、④米企業の日本売上ガイダンス。
高市早苗氏、茂木敏充氏、小泉進次郎氏が首相になった場合の想定シナリオ
高市早苗 内閣シナリオ(拡張財政+経済安保色が濃い)
政策コンパス
- 財政:景気下支えの「戦略的な財政支出」を明言。アベノミクス的色彩(減税より補助・投資の積み増し)。
- 金融:利上げに慎重(市場は“タカ派の財政・ハト派の金融”と評価)。
- 産業・安保:半導体・経済安保(サプライ網強靭化)を重視。過去に経済安全保障担当相。
- エネルギー:原子力回帰・SMR/核融合の推進に前向き。
- 外交:保守・安全保障強化(対中関係は硬め)。
マクロの型
- 円は軟化バイアス/JGB(超長期)は利回り上昇寄り(赤字拡大観測+金融緩和長期化観測)。
日本株:恩恵セクター(順)
- 輸出主力(自動車・機械・装置)=円安メリット(例:7203トヨタ、6301コマツ、8035東エレ)。
- 保険・銀行=長短金利上昇の恩恵(8750第一生命、8306三菱UFJ)。
- 半導体/経済安保テーマ=補助金・官需追い風(製造装置・材料)。
- 原子力関連=再稼働/SMRテーマ。
日本株:逆風
- J-REIT/高配当ディフェンシブ(金利上昇で相対魅力度低下)、輸入コスト敏感な内需小売。
米国株への波及
- 円安で日本売上のUSD換算は目減り(多国籍消費・ラグジュアリー等)。
- 日本株ETFでは**通貨ヘッジ型(DXJ)>非ヘッジ(EWJ)**の相対。
実務ポイント
- 短期は「輸出・金融・半導体装置」オーバーウェイト/REITや電力ガスは軽め。
- 通貨感応度の高い銘柄は為替前提(USD/JPY)を見直し。
茂木敏充 内閣シナリオ(中道路線+通商・改革実務派)
政策コンパス
- 財政:一貫して財政規律を重視。2019年の経済演説で消費税10%引き上げの必要性と基礎的財政収支黒字化を強調。
- 通商/外交:CPTPPの主導・自由貿易の旗振り役、交渉巧者(実績)。
- 経済運営:過度なバラマキに距離、成長投資は選択と集中。
マクロの型
- 不確実性後退で円は自律反発しやすい/超長期金利の過度な上振れは抑制。
日本株:恩恵セクター(順)
- 内需・サービス/REIT=金利の落ち着きと政策の予見可能性でリリーフ。
- 商社・物流=通商活性化の恩恵。
- 外需輸出も中立〜ややプラス(円の過度な安値修正で採算は安定)。
日本株:逆風
- 赤字前提の補助金依存テーマは厳選に(選択と集中)。
- 長期に極端な円安前提のトレードは見直し。
米国株への波及
- 通商安定は日米サプライチェーン銘柄にプラス(半導体装置・自動車部材)。
- 為替が落ち着けば、米多国籍企業の日本売上の翻訳差損は緩和。
実務ポイント
- バランス型配分へ回帰:内需(小売・不動産・REIT)の戻り取り+商社や物流の上方シナリオを段階的に。
- 為替ヘッジ比率を中立〜やや低下へ。
小泉進次郎 内閣シナリオ(環境・生活者重視×コミュニケーション力)
政策コンパス
- 環境:環境相時代から“脱プラ/脱炭素”を前面化。発言はポピュリスト色もあるが環境志向は一貫。
- 原子力:2019年は反原発寄りの発言。ただしエネルギー安全保障の文脈で現実路線へシフトの示唆も(資源高以降)。
- 生活者対策:物価・食料(コメ価格)対応で人気取りを狙う政策運営観測。
- 経済運営:マクロ経済の具体像は不透明(経験面は課題)。最新報道も“政策の不確実性”を指摘。
マクロの型
- 初期は不確実性プレミアムで円・金利とも振れやすい。物価対策(補助・規制)を強めると財政拡張寄りに傾きやすい。
日本株:恩恵セクター(順)
- グリーン/循環経済(再エネ、蓄電池、リサイクル、EV部材)。
- 消費関連(物価対策の直接支援・ポイント還元等が出れば短期押し上げ)。
- 農業テック・食品流通(コメ・生活必需の価格安定策がテーマ化)。
日本株:逆風
- エネルギー・原子力は方針次第で振れ幅大(反原発色が強まると原子力関連は不安定)。
- 市場は政策の具体性不足に敏感=金利・為替のボラ拡大でREITや高バリュエーション銘柄が振らされやすい。
米国株への波及
- グリーン供給網(再エネ・蓄電池素材)には日米連動のテーマ化余地。
- 逆に日本の原子力にブレーキなら、米ウラン/原子力供給網の日本向け期待は減速。
実務ポイント
- テーマ株は“グリーン+生活者支援”に寄せる一方、原子力はヘッジ的に薄く。
- 政策の確度が見えるまで為替ヘッジはやや厚めでボラ管理。
横断の比較サマリー
- 円・金利:高市(円安・長金利↑)>小泉(不確実性で振れ大)>茂木(安定・中庸)。
- 政策の予見性:茂木(高)>高市(中:方向明確)>小泉(低:具体像待ち)。
- 日本株の主役:
- 高市=輸出・金融・半導体/原子力
- 茂木=内需/REITのリリーフ+通商敏感株
- 小泉=グリーン/生活必需・食品流通
注:いずれのケースでも、LDP内の勢力拮抗・少数与党化が政策遂行力を制約する可能性は織り込み必要。総裁選は10/4見込み。マーケットは候補者の財政スタンスとエネルギー方針に最も敏感です。