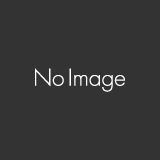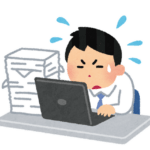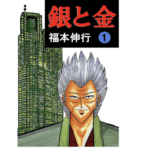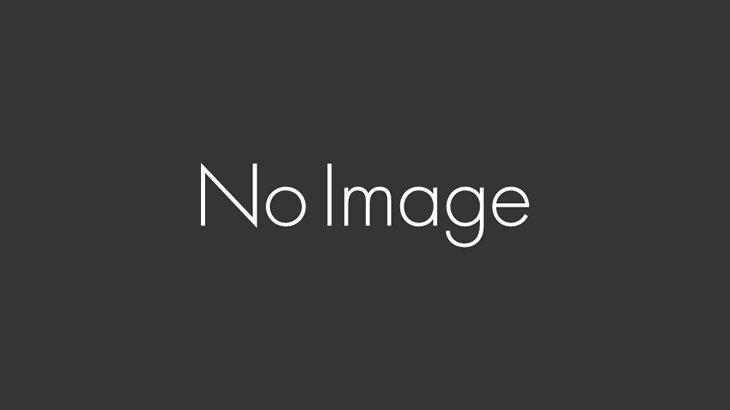目次
【米国株】相場下落時に「やった方が良いこと」と「やってはいけないこと」
今は好調ですが、いつか不調になり下落局面を迎えることになります。その時に備えて、やった方が良い事とやってはいけないことをChatGPTに整理してもらいました。間違っているかもしれないので参考程度にどうぞ。
相場下落時「やった方が良いこと」10
- 事前の投資計画を再読・固める:目的・期間・最大ドローダウン・損切/買い増し条件を紙1枚に再掲。
- 定期積立を止めない:オート積立は継続。余力があれば“増額”ではなく“回数分割”で買付。
- ルールベースのリバランス:目標配分から±5pt or 相対25%ずれでリバランス(5/25ルール)。
- 買付リストの更新:注目銘柄の“妥当レンジ”を指標(売上/FCF成長、営業CF、PER/PSR、配当余力)で数値化し、指値を段階分割(例:3~5本)。
- キャッシュと短期債の活用:生活防衛資金(3~12か月)を死守しつつ、余力はT-Bill/MMF等の待機口へ退避・戦力化。
- 税制最適化:特定口座の損出しで損益通算・3年繰越を確保。NISAは損益通算不可なので、リバランスは課税口座中心で。
- 通貨リスク管理:円安・円高でドル転/ヘッジ比率を見直し(米国資産比率×為替で過度集中を避ける)。
- ポジションサイズ縮小:ボラ上昇局面は1トレードのリスクを資産の0.5~1%に抑える等、サイズでコントロール。
- 情報ダイエット:口座確認は週1回など頻度を決め、SNSは“リスト化した一次情報”のみを見る。
- 記録を残す:取引日誌に「根拠・代替案・出口条件・感情」をセットで記録。次回下落時の再現性が上がります。
相場下落時「やってはいけないこと」10
- 計画なきナンピン:根拠/上限のない平均単価下げは“損失の先延ばし”になりがち。
- レバレッジで取り戻そうとする:信用・先物・高レバETFでの倍返しは致命傷の典型。
- 損切りルールの破棄:例外を作ると次も例外になる。最大損失ルールは厳守。
- 一気買い・全力投下:底は誰にも分からない。資金は段階と期間で分散。
- 生活防衛資金に手を付ける:売却期限のある資金でリスク資産を増やさない。
- SNSの噂で売買:一次情報(決算・開示・統計)不在の“断片”で意思決定しない。
- 通貨・セクターの片張り:為替ノーヘッジの過度集中や単一テーマ偏重はドローダウンを深くする。
- コスト・税金を無視:為替手数料、信託報酬、スプレッド、税の繰越控除などの積み上がりを軽視しない。
- ポジポジ病:やることが無いのにトレードで気を紛らわす。待つのも戦略。
- 時間軸の混同:長期枠の銘柄を短期ノリで、短期枠を長期放置で“塩漬け”にしない。
やった方が良いこと(TOP3)
1) 定期積立を止めない
- なぜ効くか:下落期は“価格の分散”が最大化される局面。積立を継続すると取得単価が自動的に切り下がり、反発局面での回復速度が上がります。反対に停止すると“上がり始めだけ買えていない”という致命的な取りこぼしが起きやすい。
- どう実行するか:月1→週1など回数分割(金額据え置き)にする。積立は原則手動にしない。反発初動でやめない。
- ありがちな失敗:ニュースで不安が増した月だけ止める→“止めた月に限って上がる”。
2) ルールベースのリバランス(5/25ルール)
- なぜ効くか:目標配分からの“ズレ”がリスク過多/過少の原因。閾値に達したら機械的に“売り高い・買い安い”が働き、リスク一定+期待リターン維持が両立します。
- どう実行するか:資産ごとに目標配分と**許容バンド(±5pt or 相対25%)**をメモ。超えたら淡々と移す。課税口座
 NISAの税制差を踏まえ、基本は課税口座側で調整。
NISAの税制差を踏まえ、基本は課税口座側で調整。 - ありがちな失敗:「もう少し待てばもっと下がる/上がるかも」で先送り→更にズレが拡大し、痛い時だけ動く羽目になる。
3) 生活防衛資金を死守しつつ、キャッシュ/短期債で“待機戦力”化
- なぜ効くか:強制売却の回避が最優先。防衛資金(3〜12か月)を隔離しておけば、相場の底で現金化せずに済む。余力はT-Bill/MMFで利回りを取りつつ、指値の弾として即時投入が可能に。
- どう実行するか:口座を分けて防衛資金を見えない化。余力は短期債/現金比率を決め、段階指値(3〜5本)で買い下がる。
- ありがちな失敗:余力を全部株に→下げが続き“弾切れ”。その後の安値を拾えない。
やってはいけないこと(TOP3)
1) レバレッジで取り戻そうとする
- なぜダメか:下落局面でレバを掛けるとボラティリティ損と追証/ロスカの二重リスク。-50%の回復に+100%が必要という現実に、レバは致命傷の確率を跳ね上げます。
- 回避策:最大レバ=0を原則。どうしてもなら限定損失(現金担保プット/カバードコール等)に限定し、想定最大損失を資産の0.5〜1%以内に。
2) 生活防衛資金に手を付ける
- なぜダメか:相場と家計リスクは同時に悪化しやすい(リストラ・副業減収等)。防衛資金に手を出すと底値での強制売却が起き、復活の芽を摘む。
- 回避策:防衛資金は別口座でロック。引き出し条件を紙で明文化(「投資目的には絶対使わない」)。
3) 一気買い・全力投下
- なぜダメか:底は事後しか分からない。全弾一発は時間分散ゼロで、さらに下がった時に“動けない”。心理的にもリスク管理不能。
- 回避策:時間×価格の二軸分割(例:期間3か月×指値3〜5本)。上がっても下がっても“次の一手”が残る設計に。
まとめの優先順位(下げ相場の行動フレーム)
- 資金繰り:防衛資金の死守 → 余力は短期債で待機
- リスク量:配分のズレをルールで戻す(5/25)
- 売買順序:積立は止めない → 段階指値で淡々と執行
リーマン(2007–09)とコロナ(2020)を「実際の時系列」に沿って、やるべき行動とやってはいけないパターンを要点でまとめる
リーマンショック(2007–2009)
相場の骨子(事実)
- S&P500は2007/10/9に高値→2009/3/9に安値(ピーク→ボトムで約-56.8%)。
- 2008/9/15 レーマン破綻、2008/10/3 TARP成立、2008/11/25 QE1発表。
フェーズ別・やるべきこと
① 高値~破綻前(2007/10~2008/9)
- 目標配分×5/25ルールを発動準備(株比率が目標−5pt/相対−25%で機械的に買い)。
- 積立は停止しない(金額据え置きで回数分割)。
- 生活防衛資金は別口座で死守、余力はT-Bill/MMFで待機化。
② 破綻直後~TARP/QE1周辺(2008/9~2008/12)
- ボラ急騰につき**1トレードの損失上限を資産0.5〜1%**に縮小。
- **段階指値(3〜5本)**で買い下がり:例)直近高値から-20/-30/-40/-50%。
- 課税口座で損出し→通算、NISAは原則触らず(リバランスは課税口座中心)。
③ ボトム形成~反発初期(2009/1~2009/5)
- 下落で株比率が目標を大きく下回る→リバランスで株を足す(“安く買う”をルールで実行)。
- 反発初動でも積立継続(上がり始めで止めない)。
- 記録:買付根拠・代替案・出口条件を日誌化→次局面で再現。
やってはいけないパターン(当時ありがち)
- レバで一括取り返し(信用・先物・高レバETF):追証→退場リスク急増。
- 積立停止→底打ちを逃す(“止めた月に限って上がる”)。
- 全力一括投入:更なる下落で弾切れ・心理折れ。
コロナショック(2020)
相場の骨子(事実)
- S&P500は2020/2/19 高値→2020/3/23 安値、下落率は約**-33%**。
- 3/3 緊急50bp利下げ、3/15 ゼロ金利+QE、3/23 “無制限QE”や各種ファシリティ、3/27 CARES法(約2兆ドル)
フェーズ別・やるべきこと
① 高値直後~急落初期(2020/2下旬〜3/上旬)
- 積立は継続、指値は時間×価格で分割(例:週次×-10/-20/-30%節)。
- 株の下げで債券/現金が相対的に増える→リバランスで株を買い。
② パニック最中(3/12前後の大波乱〜3/23底)
- 執行は定時・定額・段階で淡々と。メディアやSNSの断片情報で方針を変えない。
- 生活防衛資金は固定、余力は短期債→指値の弾に。
- 損出しで税最適化、ポジションサイズは縮小。
③ 政策発動~反発初期(3/23以降)
- 無制限QE/財政成立確認でも“天井売り・底買い”は狙わない→積立とリバランス継続。
- 反発で配分が偏るなら機械的に目標へ戻す(利益確定=悪ではない)。
- 取引日誌で感情と根拠を記録→次の急落で再利用。
やってはいけないパターン(当時ありがち)
- 底割れ恐怖で積立停止→最短級のV字反発に取り残される。
- レバ全力/ショート過多→ボラ拡大と政策ショックで踏み上げ・強制決済。
- 防衛資金に手を付ける→家計ストレスと相場下落が同時進行で、底での強制売却に繋がる。
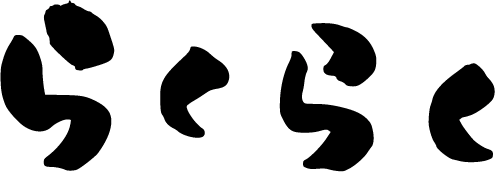

 NISAの税制差を踏まえ、基本は課税口座側で調整。
NISAの税制差を踏まえ、基本は課税口座側で調整。